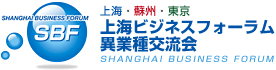中国と日本の会計相違点② 発票制度中国会計コーナー
中国の会計準則には、「発生主義」原則を明記している。しかし、その発生主義は多くの外資系企業にとって、「現金主義」ではないかと誤解されやすい。主な理由は「発票主義」の存在にある。
「発票」の日本語訳は領収書である。日本と異なり、中国の領収書は文具屋で購入することができない。所轄する税務局に「税務登録」をした企業は、一冊の「発票購買手冊」をもらえる。その「発票購買手冊」によって、税務局から発票を購入する。(下記を参照)
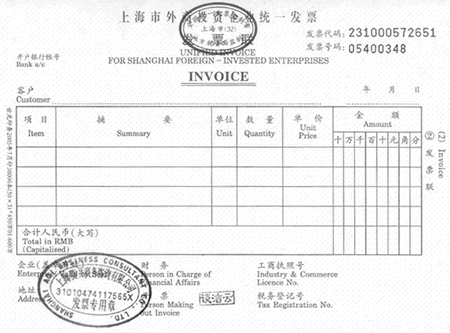
発票は以下の条件が揃うと有効になる
- 税務局の捺印:税務局から購入したことを証明する
- 発行日付:発行企業の売上確定日付となる一方、取得する企業の費用、資産計上日付となる。
- 金額(単価、数量):アラビア語数字と中国数字を併記する
- 発行会社の捺印
- 相手企業名
- 発票作成者のサイン或いは捺印
※発票の偽造を防止するために、多くの発票に透かしがある。
「発生主義」の発生基準は「発票」である
日本では「請求書」に基づいて売上を計上し、代金回収が確認できたら領収書を発行する商習慣があるが、中国では原則的に発票を発行しない限り、売上計上をしてはいけない。
日本の商習慣をそのまま中国でも適用できると考えた日系企業経営者が「請求書」の発行時点で売上計上しようとして、中国人の会計師に拒否されることが多い。一方、それらの日本人経営者は代金回収をしないかぎり発票を発行しないということに固執するので、日本の商習慣による売上と中国基準の売上に時間差が生じる。
代金回収時点での領収書の発行と、発票発行時点での売上計上という日中両方の商習慣を混在して考えると、確かに中国の「発生主義」は「現金主義」に見える。
しかしながら、中国の「発票」が日本語で「領収書」に翻訳されても、実際には「請求書」の役割もあるのである。英語が印刷されている「発票」には「INVOICE」という表現が使用されており、その意味は「領収書」ではなく「請求書」である。
「発票」が「領収書」と「請求書」の合体であることを理解すれば、「発票主義」に基づく「発生主義」も理解しやすくなる。
例)1月10日に販売した1,000RMBの商品代金を2月10日全額回収した場合、下記の会計処理を行う。
①1月10日、商品の引渡しと同時に「発票」を発行する
借方:応収帳款 1,000RMB
貸方:主営業務収入 1,000RMB
② 2月10日、商品代金を全額銀行回収した
借方:銀行存款 1,000RMB
貸方:応収帳款 1,000RMB
「発票」は売上計上のための最重要の伝票であり、日本の領収書の役割は、銀行入金証明または現金受取書がすることになる。売上だけではなく、費用、資産の計上も取引先からの「発票」の取得時点によって確認されることがほとんどである。
中国国内すべての企業が「発票制度」が適用されているので、政府は企業の売上・費用等を正確的に把握できる。販売側の企業が売上隠蔽をしようとしても、相手企業は「発票」を取得しなければ費用計上ができないため、必ず販売側企業にこれを請求する。税務局で購入した連番の「発票」を発行する販売側企業は結局隠蔽することができなくなる。
このような厳しい「発票制度」の確立によって、所轄する政府部門は企業の経営活動、納税対象の算出などを把握しやすくなる。一方、企業はこの「発票主義」を理解したうえで真面目に実行しなければ、会計処理、税務処理を不正に行っていると認定される可能性が大きい。
参考:「中国における会計制度と実効のある経理関係社内規程」(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)
※当ページの内容は掲載当時の情報であり、将来に渡ってその真正性を保証するものではありません。
※法令等の改正や運用の変更等により現在と異なる場合があります事を、予めご了承ください。